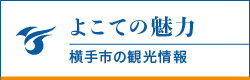大雨に対する農作物等の被害防止対策について
大雨に対する農作物等の被害防止対策をご確認ください
共通事項
ほ場の見回り等については、事故防止の観点から気象情報などを十分に確認し、二次被害にあわないよう留意のうえ行うこと。
水稲
- 冠水した場合には、速やかに排水を図る。
- 冠水した稲体は、水分調節や肥料吸収等の機能が低下していることから、田面の過度の乾燥に注意する。
- 冠水を受けたほ場では病害虫が発生しやすくなることから、発生状況に注意し、必要に応じて防除を行う。特に、いもち病の発生には注意する。
- ほ場内への漂着物等は、収穫時の事故につながるため、除去に努める。
- 畦畔や用排水路等の点検・修繕を行い、適切な水管理に務める。
大豆
- 排水路を点検し、速やかに排水を図る。
- ほ場内の明渠の水の流れを確認し、溝が崩れていたり浅くて流れない場所があれば手直しして、排水に努める。
- 浸冠水したほ場は、病害虫が発生しやすくなることから、発生状況に注意し、必要に応じて防除を行う。特に、茎疫病の発生が懸念されるため、こまめなほ場巡回により発病株の除去に努める。
野菜・花き
- ほ場内の停滞水は、酸素供給量の不足によるや根腐れ・疫病などの原因となるので速やかに排水する。
- 浸冠水により茎葉が汚れた場合は、ほ場の排水に努めるとともに可能な限り速やかに散水などを行い、汚れを落とす。
- 風雨等により損傷した茎葉の整理を行い、病害予防(殺菌剤散布)に努める。
- パイプハウス内に水が浸入した場合、速やかに排水を行うとともに、換気を十分に行い、土壌の乾燥を図る。施設内では湿度の上昇によって、灰色かび病などの発生が多くなるので、換気扇などを活用し、強制的な換気に努める。
- 根腐れや茎葉汚損により草勢低下が懸念される場合は、曇天時に液肥の葉面散布等を行い生育の回復に努める。
- 生育の回復や商品化が困難な場合は、早期に被害株を整理する。生育期間の短い葉菜類等では、播き直しを行う。
果樹
- 滞水している園地では、明きょなどにより速やかな排水に努める。
- 土砂が流入した園地では、なるべく早く土砂を取り除き、枝葉に付着した泥などの汚れを洗い落とす。
- 樹が倒伏した場合は、できるだけ早く起こして支柱などで固定する。また、着果量制限や堆肥などによるマルチで、樹勢低下を防ぐ。
- 病害の発生を防ぐため、防除間隔が空かないように次回の防除を早めるか、追加防除を実施する。なお、防除を行う際には、農薬使用基準を遵守し、適切に実施する。果実病害などが発生した場合は、見つけ次第摘果する。
- 葉色の低下などが認められた場合は、着果量を制限し、液肥などの葉面散布で樹勢回復を図る。
畜産
- 施設内に浸水があった場合は、停滞水やゴミなどを速やかに排除するとともに、水洗・消毒の実施により疾病や衛生害虫の発生の予防に努める。
- カビ等の発生防止のため、扇風機等の活用により強制的に換気し湿度を下げる。
- 損傷した施設については、応急措置を講じ、風雨の侵入を防止する。
- 冠水等の被害を受けた飼料は、原則家畜への給与を中止し、速やかに新たな飼料の確保に努める。
- 当該飼料を使用せざるを得ない場合は、栄養価や嗜好性等にも配慮し、家畜の生産性が低下することのないように注意する。
- 浸水や冠水があった飼料作物のほ場では、速やかな排水に努める。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
農林部農業振興課農業政策係
〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局3階)
電話:0182-32-2112 ファクス:0182-32-4037
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。